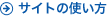自己紹介
こんにちは。2021年度青年海外協力隊2次隊でマラウイに派遣されている船田ひかり(ふなだひかり)です。この度、30歳という1つの節目を迎える前に「小さい頃に憧れていた青年海外協力隊に挑戦したい!」と思い、2年間休業させていただき、青年海外協力隊に参加いたしました。
現在は、首都リロングウェから50km程離れたところにある村のカブドゥラ小学校で算数を教えています。
マラウイはどんな国?
みなさんはマラウイという国をご存知でしょうか?簡単にマラウイという国を紹介すると、
・アフリカの南東に位置(隣接国はタンザニア・ザンビア・モザンビーク)
・面積は118,484㎢(日本の3分の1、北海道と九州を合わせたぐらい)
・公用語はチェワ語と英語(公用語の他にも地域によって違う言語が使われている)
・世界で9番目の広さを誇るマラウイ湖がある(マラウイの国土の20%以上を湖が占めています)
・独立以来、対外戦争・内戦が起きていないことから、国のニックネームは「Warm heart of Africa」(他のアフリカ諸国に比べると治安も良い)
・主食は「シマ」(トウモロコシの粉にお湯を加えてねったもの)、おかずは魚やお肉のトマト煮がポピュラー(村のご飯屋さんは牛・豚・鶏・ヤギと肉の種類は選べますが調理法はトマト煮一択)

※ある日の昼食
マラウイは最貧国の一国とされています。
世界銀行の調査(2018年)によると、国民のほとんどが1日1.9ドル以下で暮らし、
国全体の電化率は11%(都市部42%、農村部4%)、
自宅で水道水が直接利用できる人口は3.1%。
数字でみると「貧しい国」「厳しい生活」というイメージが湧くと思います。
私もマラウイに赴任する前は、マラウイの人々はみんなガリガリに痩せて、生活に困窮して、苦しい思いをしていると思っていました。
確かにそういう人もいるかと思いますが、私の住んでいる村の人はみんなよく笑い、よく食べ(ふくよかな人が多い)、とっても元気で、貧困に苦しんでいるような印象は受けません。
そして都市部はショッピングモールやレストラン、カフェもたくさんあり、一般的にイメージされる「後発開発途上国」のイメージとは違うように思います。
本当の国の姿は、インターネットや文献の情報だけではわからないことを痛感しました。


※首都のショッピングモール


※家の近くにある井戸 ※村のマーケット
イメージを変えたい
私がマラウイに赴任すると周囲の人へ報告すると、「アフリカの国?みんな腰に葉っぱを巻いて、槍を持って生活しているところに行くの?」と言われることがありました。そのような生活をしている民族もアフリカの一部では存在しますが、アフリカの国に住む全員がそのような生活をしているわけではありません。最近では近代化が進み、日本と大差のない生活ができる地域も多くあります。
私がマラウイで活動する期間は2年間です。この2年間で任地の子どもたちに学ぶ楽しさを伝えるとともに、現地の様子をできる限り伝え、アフリカ・マラウイを多くの人に知っていただけると嬉しいです。

※全校集会の様子


※近所の子どもたち ※首都から村に向かう道