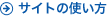危ないと思ったら「自分の命は自分で守る」という心構えで、早めに避難しましょう。
安全に避難するために!
- 避難の指示があった場合は、すみやかにその指示に従いましょう。
- 隣近所の人たちに声をかけて、集団で避難しましょう。
- 避難する前に、もう一度火元の確認をしましょう。
(ガスの元栓・プロパンガス・電気器具のスイッチ・電気のブレーカー) - 徒歩で避難しましょう。
- 持ち物は最少限にまとめて。
- ヘルメット(防災ずきん)で頭を保護し、長袖、長ズボン等の安全な服を着用しましょう。
- ラジオ、テレビなどの災害情報をよく聞き、あわてずに落ち着いて行動しましょう。
- 降灰を吸い込まないように注意しましょう。
- がけや川のそばは、なるべく避けて避難しましょう。
- なるべく指定された避難場所に避難しましょう。
避難広報
- 広報車等での広報
火山噴火や地震が発生し津波のおそれがある場合、広報車、消防車等により住民への避難 広報が実施されます。 - サイレンでの広報
消防は、必要に応じてサイレンを近火信号に準じて吹鳴し避難広報が実施されます。
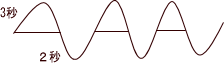
警戒区域の設定
災害が発生し、または発生しようとしている場合において、住民の生命を守るために特に必要があると認めるときは警戒区域が設定され、災害応急対策従事者以外の立ち入りを制限若しくは禁止し、住民の退去が命ぜられます。| 発令者 | 設定の要件 | 根拠法令 |
|
本部長
(市長)
|
災害が発生し、または災害が発生しようとしている場合において、市民の生命、身体に対する危険を防止するために特に必要と認めるとき | 災害対策基本法第63条 |
|
警察官
又は
海上保安官
|
上記の場合において、市長若しくはその委任を受けた市職員が現場にいないとき、若しくは市長から要求があったとき | 災害対策基本法第63条 |
| 自衛官 | 災害派遣を命ぜられた部隊の自衛官は、市長若しくはその委任を受けた市職員が現場にいない場合で、他に職権を行う者がいないとき | 災害対策基本法第63条 |
| 消防職員 | 災害の現場において、消防活動の確保を主目的に設定 | 消防法第36条において準用する同法第28条 |
避難所の開設
災害対策本部では、指定した避難所に職員を派遣し、施設の管理者と連携して可能な限り多くの避難所の開設を行います。避難所の開設準備は、次のとおりです
- 居住スペース、共用スペースなどの割り振り
- 駐車場の確保
- 備品の確保
- 避難者名簿等の確保
- 備蓄品、生活必需品の確保
- 飲料水・食料の確保
避難所・避難場所
| 種類 | 施設 | 機能 | 適応災害 |
| 避難所 | 各学校 |
|
|
| 避難場所 | 公園 |
|
|
避難者の把握
1.避難所での把握
避難所に派遣された職員(以下「避難所職員」という。)は、避難所において避難者世帯カードを配布し、避難者に記入してもらう。避難者世帯カードは回収し、避難者名簿を作成します。
2.親戚・知人宅等の避難者の把握
親戚・知人宅に避難した避難者の把握は、原則として避難者自らの連絡によるものとします。連絡された方の、避難先、連絡方法などを記載した避難者名簿を作成します。
テレビ、ラジオ、新聞等により、親戚・知人宅等に避難した避難者に対し、それぞれの対策本部に連絡するように広報します。
3.避難者の管理
- 避難者の動向の把握
避難者が移動する場合は、避難者の申告により避難者名簿を改訂し、常に最新の所在を把握します。 - 出入者の把握
避難所では、通勤、通学、外出など避難者の入退所を記録します。
避難所の運営
避難所自治組織の結成
1. 自治組織の結成避難所の運営は、原則として避難者による自治とします。
自主防災組織や町内会組織等を基本に自治組織を結成するよう働きかけます。
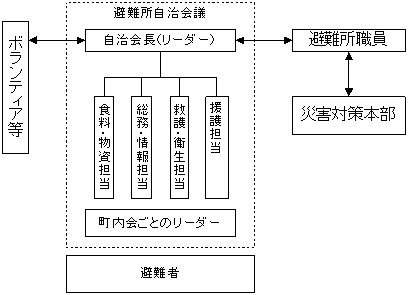
避難所自治組織では、自治会長、各担当リーダー、町内会ごとの班を定め、必要に応じて避難所自治会議を開催します。
避難所職員は、自治会長からの要望等の相談にあたり、災害対策本部、施設管理者との調整にあたります。
ボランティア団体や外部機関との交渉は自治会長があたります。