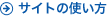老齢基礎年金
保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間の合計が10年(120か月)以上ある人が、65歳に達したときに請求できます。本人の希望によって受給開始年齢を早めたり(繰上げ請求)、遅らせたり(繰下げ請求)することができます。
※繰上げ請求を希望する場合は、年金額が減少するほか各種制限を受けるため、手続きの前に必ず確認してください。
保険料納付済期間
- 国民年金保険料を納めた期間
- 厚生年金保険・共済組合等の加入期間のうち、20歳以上60歳未満の期間
- 第3号被保険者期間
保険料免除期間
- 保険料を全額免除された期間(障害年金、生活保護法による生活扶助を受けていた期間など法定免除期間を含む)
- 保険料を4分の3免除された期間のうち、4分の1の保険料を納めた期間
- 保険料を半額免除された期間のうち、半額の保険料を納めた期間
- 保険料を4分の1免除された期間のうち、4分の3の保険料を納めた期間
- 保険料の納付猶予・学生納付特例を受けた期間
合算対象期間
「カラ期間」とも言われ、老齢基礎年金の受給額には反映されませんが、受給資格期間には算入される期間のことです。国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間などが、これにあたります。(昭和61年3月以前に厚生年金加入者の配偶者だった期間や平成3年3月以前に学生だった期間など)
詳しくはこちら(日本年金機構のホームページへ)
<支給される年金額>
老齢基礎年金は、20歳から60歳に達するまでの40年間、すべての期間、保険料を納付した人に令和7年度は831,700円(70歳以上は829,300円)が支給されます。保険料納付済期間が40年に満たない場合は、不足する期間に応じて減額されます。計算方法
| 831,700円 (70歳以上は 829,300円) |
× | 保険料納付済月数+(保険料全額免除月数×2分の1)+(保険料4分の3免除月数×8分の5) +(保険料半額免除月数×4分の3)+(保険料4分の1免除月数×8分の7) |
| 加入可能年数(下記参照)×12 | ||
| |
※この計算式の保険料免除期間には、学生の保険料納付特例期間の月数および50歳未満の方を対象とした保険料の納付猶予期間の月数は含まれません。
加入可能年数
| 生年月日 | 年数 |
|---|---|
| 昭和 9年4月2日~昭和10年4月1日 | 33年 |
| 昭和10年4月2日~昭和11年4月1日 | 34年 |
| 昭和11年4月2日~昭和12年4月1日 | 35年 |
| 昭和12年4月2日~昭和13年4月1日 | 36年 |
| 昭和13年4月2日~昭和14年4月1日 | 37年 |
| 昭和14年4月2日~昭和15年4月1日 | 38年 |
| 昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 | 39年 |
| 昭和16年4月2日以降 | 40年 |
障害基礎年金
次の1~3に該当する人が受給要件を満たすときに請求できます。- 国民年金加入中の期間に初診日がある病気・けがで障害が残った人
- 国民年金の加入者であった人で、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の期間に初診日がある病気・けがで障害が残った人
- 20歳前の期間に初診日がある病気・けがで障害が残った人(所得による支給制限があります)
《受給要件》
- 初診日の前々月までの期間に、保険料の納付や免除・猶予期間が3分の2以上あるか、直近の1年間に保険料の滞納がないこと。(20歳前に初診日がある人は除きます)
- 初診日から1年6ヵ月経過した日またはそれ以前に症状が固定した日(障害認定日)に、障害の程度が国民年金法に定める1級または2級(身体障害者手帳の等級とは必ずしも一致しません)に該当するとき。(20歳前に障害認定日がある人は、20歳の誕生日の前日が障害認定日になります)
- 障害認定日に障害の程度が軽かったため、障害基礎年金を受けられなかった人が、その後65歳になるまでの間に障害の程度が国民年金法に定める1級または2級になったとき。(65歳になる前に請求)
なお、初診日当時、厚生年金に加入または第3号被保険者の方は、年金事務所にご相談ください。
<支給される年金額(令和7年度)>
- 1級の障害 … 年額1,039,625円(70歳以上は1,036,625円)
- 2級の障害 … 年額831,700円(70歳以上は829,300円)
子の加算額
| 1人目・2人目の子 | 一人につき 239,300円 |
|---|---|
| 3人目以降の子 | 一人につき 79,800円 |