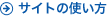●定額減税についてはこちら
財政部市民税課 令和6年度個人住民税の定額減税について
国税庁 定額減税 特設サイト(外部サイトへ移動します)
1.調整給付の対象者
定額減税可能額が「※令和6年分推計所得税額」又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方
※令和6年分推計所得税額:令和5年分の所得等の情報を参考に、国が定めた算定基準に基づき推計した税額です。
2.定額減税可能額
・所得税分=3万円×※減税対象人数
・個人住民税所得割分=1万円×※減税対象人数
※減税対象人数:納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)
控除対象配偶者及び扶養親族について、国外居住者は対象外となります。
3.調整給付金の支給額
定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合、上回る額を1万円単位に切上げて算定した額を支給します。
・調整給付金の支給額=(1)+(2)(1万円単位で切上げ)
(1)所得税分控除不足額
定額減税可能額(3万円×減税対象人数)-令和6年分推計所得税額=ア 所得税分控除不足額(※アが0円を下回る場合は0円)
(2)個人住民税分控除不足額
定額減税可能額(1万円×減税対象人数)-令和6年度分個人住民税所得割額=イ 個人住民税分控除不足額(※イが0円を下回る場合は0円)
【調整給付金の計算例】 ※「控除対象配偶者及び扶養親族がいない」場合
| パターン | (1)所得税分 | (2)個人住民税所得割分 | 支給額 控除しきれない額(1)+(2) |
|
| 例1 | 所得税・住民税の両方に控除しきれない額がある場合 | 定額減税可能額 3万円 令和6年分 推計所得税額 2万2千円 控除しきれない額 8千円 |
定額減税可能額 1万円 令和6年度分 個人住民税所得割額 4千円 控除しきれない額 6千円 |
(1)+(2)=1万4千円 (1万円単位で切上げ) ↓ 調整給付金支給額 2万円 |
| 例2 | 所得税・住民税の一方に控除しきれない額がある場合 | 定額減税可能額 3万円 令和6年分 推計所得税額 2万2千円 控除しきれない額 8千円 |
定額減税可能額 1万円 令和6年度分 個人住民税所得割額 2万円 控除しきれない額 0円 |
(1)+(2)=8千円 (1万円単位で切上げ) ↓ 調整給付金支給額 1万円 |
4.調整給付金の申請方法
調整給付金の対象となる方には、令和6年7月10日(水)から順次、支給確認書(以下、「確認書」)を送付します。
確認書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒に入れて返送してください(本人確認及び、口座情報が確認できるものの写しの添付が必要な場合があります。届いた確認書等をご確認ください)。
確認書の返送期限:令和6年10月31日(消印有効)
※返送期限後は給付できませんので、お早目に提出してください。
5.調整給付金の支給時期
市が確認書を受理した日から3~4週間後に支給予定です。
なお、振込日が確定し次第、市から振込日の記載されたハガキを送付します。
※通知書の発送直後は多くの確認書を受理するため、振込みまでにお時間がかかります。
6.調整給付額に不足が生じた場合
税の更正等により令和6年度住民税所得割額に変更が生じ、調整給付額に不足が生じた場合、令和6年中には調整を行いません。令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、当初給付額に不足があること等が判明した場合には、令和7年中に追加で給付する予定です。詳細については、国から情報が得られ次第、本ページ等でお知らせします。
調整給付額に不足が生じうる例
・令和5年又は令和6年分所得税額や令和6年度個人住民税額の決定後に変更が生じた場合・所得税額に住宅ローン控除や寄付金控除等があり、定額減税しきれない場合
・令和6年1月1日以降にこどもが生まれた等、扶養親族が増えた場合
7.注意事項
この定額減税補足給付金(調整給付金)は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。
8.関連情報
●内閣官房 新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(外部サイトへ移動します)
よくある質問
Q1 定額減税補足給付金(調整給付金)とはどのような制度ですかA1 令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割から1万円の定額減税が実
施されます。その際に、減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を給付金として支給す
るものです。
Q2 定額減税補足給付金(調整給付金)を受け取るためにはどのような手続きが必要ですか
A2 支給対象と見込まれる方に、令和6年7月10日(水)から支給確認書を郵送しております。
支給確認書が届きましたら、内容をご確認のうえ、返送してください。
Q3 定額減税補足給付金(調整給付金)は、いつ振込されますか
A3 返送していただいた支給確認書に不備がないことを確認した日から3~4週間程度で振込され
ます(支給確認書発送直後の時期は、支給が遅れる場合があります)。
Q4 令和5年中は収入がなく、令和6年度個人住民税が非課税ですが、定額減税補足給付金(調整給
付金)は支給されますか
A4 令和6年分推計所得税及び令和6年度個人住民税が非課税の場合、定額減税補足給付金(調整給
付金)の対象外となり、支給されません。
Q5 住宅ローンやふるさと納税などの税額控除を受けている場合はどうなりますか
A5 定額減税は、住宅ローンやふるさと納税などの税額控除後の所得税額や個人住民税所得割額に
対して行われます。税額控除適用後に、所得税額や個人住民税所得割額が課税される場合、定額
減税で控除しきれない分を給付します。
Q6 対象者が死亡した場合、定額減税補足給付金(調整給付金)は支給されますか
A6 1.対象者がお亡くなりになった日が令和6年1月1日以前の場合
定額減税補足給付金(調整給付金)の対象外となります。
2.対象者がお亡くなりになった日が令和6年1月2日以降の場合
給付申請を行った後にお亡くなりになった場合は、対象者に給付されます。給付申請を行
うことなく亡くなられた場合は給付されません。
Q7 令和6年1月2日以降に日本に入国した場合、定額減税補足給付金(調整給付金)の対象とな
りますか
A7 令和6年1月1日時点で国内に居住していない場合は、令和6年度個人住民税が課税されませ
んので、令和6年度の定額減税補足給付金(調整給付金)の対象となりません。
Q8 令和6年中に子どもが生まれる予定です。定額減税補足給付金(調整給付金)の対象となります
か
A8 令和6年1月1日以降に生まれた子は、令和6年度個人住民税の扶養の対象となりません。所得税
は、年末調整または確定申告等により定額減税を受けることができます。この結果、定額減税補
足給付金(調整給付金)に不足が生じる場合には、令和7年以降に追加で給付を行う予定です(時
期及び手続きは未定です)。
Q9 令和6年分の所得税額の確定等により、定額減税補足給付金(調整給付金)が不足しているこ
とが判明した場合はどうなりますか
A9 令和6年分推計所得税額は令和5年所得等を基に算定しており、実額による算定ではないた
め、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、定額減税補足給付金(調整給付
金)に不足が生じる場合には、令和7年以降に追加で給付を行う予定です(時期及び手続きは未
定です)。
臨時特別給付金に関する問い合わせ
生活者支援給付金室受付窓口(市役所第二庁舎1階会議室)連絡先:0144-32-6266
受付時間:8時45分から17時15分(土日祝日は除く)