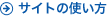消防団の歴史
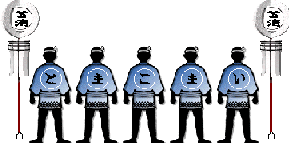
消防団の歴史は古く、1718年(享保3年)に江戸南町奉行の大岡越前守が江戸の町にとび職の人(土木工事や建築の職人)を中心として「いろは四八組」の「町火消し」を組織したのが始まりといわれています。
この町火消し制度は、「江戸の町は、江戸の庶民の手で守らせる」という、いわゆる自衛、自治の考えでした。「いろは」等の名前の付いたそれぞれの火消し組は、お互いの名誉にかけて競い合って働きました。
その後名称は、明治から大正にかけ「消防組」、昭和の戦時中には警察の補助機関として「警防団」、そして戦後警察から分離し「消防団」が組織されました。このように消防団は様々な変遷を経て今日に至っています。
「自分の住む街は、自らが守る」の精神は、現在も消防団に受け継がれています。
消防団とは?
消防団と消防本部(消防署)の違いは?
消防本部(消防署)は、消防活動、事務等に従事する消防職員(消防吏員)を擁する常設の消防機関です。火災、救急救助等のあらゆる災害に出動し、災害現場の第1線で活動するとともに、消防の企画立案等の事務を執り、消防設備の指導、危険物の規制などの火災予防活動等に従事します。消防団は、地域に居住している住民が、「自分の住む地域は、自らの手で守る」ことを基本に消防職員と協力して活動するために編成された地域社会に奉仕する団体であり、ボランティア的な性格が強い組織です。
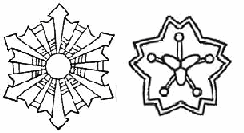
(消防章)・(消防団記章)
団員は普段それぞれの職業を持ちながら、災害が起きた時、消防団員として出動する非常勤特別職の地方公務員です。そのため、訓練・研修等を定期的に実施して、いつ災害が発生しても活動できるように備えています。
日本全国には、2,198団の消防団が組織され、83万1,982人の消防団員が活躍しています。(平成31年4月1日現在)

(消防訓練大会)
消防団の組織
本市の消防団員数は、消防団長以下223名(定員287名)です。団本部・女性分団と市内を9箇所に区分し、それぞれの地域に分団があります。(令和2年4月1日現在)組織の運用、厳然たる指揮命令系統を確立するために、消防団では階級制度をとっています。この階級は現在、団長・副団長・分団長・副分団長・部長・班長・団員の7階級に分けられています。

消防団の処遇
- 一般的にいう給料はありませんが、年額報酬・出動手当が支給されます。
- 制服・作業服等の被服が貸与されます。
- 訓練や災害活動中にケガをした場合は、補償制度があります。
- 退職時(5年以上勤続)には、退職報償金が支給されます。
とまこまい消防まとい隊
消防伝統演技の木やり唄、まとい振り、はしご乗りは江戸時代を起源としており、団結力や勇敢さを表現したものです。本市の消防団も市民に親しまれる消防団を目指して、平成10年に消防本部、消防団の熱意と努力で約60年ぶりに復活させ、「とまこまい消防まとい隊」 と称し出初式等で市民に披露し称賛されております。
隊員は現在約70名の消防団員により編成され、使用している「まとい」や「はしご」は、隊員が手作りで作成したものです。


TEAM-アイリス(女性分団)
とかく「男の世界」と思われがちな消防団ですが、全国で2万6,625人(平成31年4月1日現在)の女性消防団員が、住民への防火指導や応急手当の普及など様々な分野で活躍しています。本市の女性消防団員も、地域住民に対する消火器の取扱い指導や、お年寄り世帯、幼稚園などで火災の恐ろしさと避難方法等について啓発し、火災による被害の無い地域を目指して活動しています。
幼い心に火の用心

高齢者世帯防火訪問

消火器取扱い指導

消防団員になるには
- 苫小牧市に居住していること。
- 年齢が18歳以上55歳まで。
- 健康で消防団活動ができること。
あなたも消防団に入団して、火災、災害に負けない強い街づくりのため、消防団活動に参加しませんか。