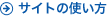制度概要
児童扶養手当制度は、父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための国の制度です。対象者
以下の条件に当てはまる児童(18歳到達後最初の3月31日までの間にある者)を監護している父または母や、父または母にかわってその児童を養育している方が対象です。また、児童が心身に一定以上の障がいを有する場合は、20歳の誕生日の前日が属する月まで延長できます。
- 父母が婚姻(事実上の婚姻を含む)を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級相当)にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からの配偶者暴力等に関する保護命令(DV)を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父母とも不明である児童
対象にならない場合
- 日本国内に住所を有しない場合
- 児童が児童福祉施設等に入所したり、里親委託された場合
- 父または母の配偶者(事実上の婚姻関係を含む)に養育されている場合(父または母が政令で定める一定以上の障がいの場合を除く。)
手続き方法
認定請求
離婚等により受給資格が生じた場合は、こども支援課(市役所1階ピンクゾーン17番窓口)で「認定請求書」を提出してください。手当は認定請求をした翌月分から、受給資格の消滅した日の属する月分まで支給されます。
認定請求に必要なもの
- 請求者の戸籍謄本
(離婚の場合、離婚年月日の記載があるもの。離婚日の記載がない場合は改正原戸籍等が必要) - 児童の戸籍謄本(児童が請求者以外の戸籍謄本に記載されている場合のみ)
認定請求以外については、「その他手続きが必要なとき」をご覧ください。
手当額(月額)
手当額は、受給資格者および扶養義務者注1の前年度の所得状況により、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。詳しくは所得制限をご覧ください。
【令和6年11月分手当~令和7年3月分手当まで】
| 全部支給額 | 一部支給額 | |
| 児童1人目 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
| 児童2人目以降 | 10,750円 | 10,740円~ 5,380円 |
【令和7年4月分手当以降】
| 全部支給額 | 一部支給額 | |
| 児童1人目 | 46,690円 | 46,680円~11,010円 |
| 児童2人目以降 | 11,030円 | 11,020円~ 5,520円 |
所得制限
受給資格者本人の前年度の所得額が下表以上である場合は、その年度(11月分~翌年10月分まで)の手当の一部または全部が停止されます。また、養育者、受給資格者の配偶者および扶養義務者注1の所得額が下表以上である場合は、手当の全部が停止されます。
扶養義務者と生計を同じくしていない場合は、ご連絡ください。
注1 扶養義務者は、受給資格者と生計を同じくしている直系血族三親等以内の親族です。
(父母、兄弟姉妹、祖父母、曾祖父母、子、孫、曾孫)
受給資格者が父母の配偶者と養子縁組をしている場合は直系血族とみなします。
| 扶養親族等の数 | 受給資格者本人 | 養育者、配偶者、 扶養義務者 |
|
| 全部支給 | 一部支給 | ||
| 0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 |
所得額
所得額=地方税法に基づく所得控除後の額(年間収入額-給与所得控除額等の必要経費)+養育費の8割相当額-8万円-諸控除注2注2 諸控除は以下のとおり
障害者控除、勤労学生控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
配偶者特別控除、医療費控除、雑損控除 地方税法で控除された額
寡婦控除 270,000円(養育者、扶養義務者のみ該当)
ひとり親控除 350,000円(養育者、扶養義務者のみ該当)
限度額に加算されるもの
- 受給資格者本人
老人控除対象配偶者または老人扶養親族の税控除がある場合 1人につき10万円
特定扶養親族の税控除がある場合 1人につき15万円 - 養育者、配偶者および扶養義務者
老人控除対象配偶者または老人扶養親族の税控除がある場合 1人につき6万円
(ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く)
支給時期
支給日は原則、奇数月の11日(土日祝日の場合は直前の金融機関営業日)です。| 支払予定日 | 支給対象月 |
| 令和7年5月9日(金) | 3月~4月分 |
| 令和7年7月11日(金) | 5月~6月分 |
| 令和7年9月11日(木) | 7月~8月分 |
| 令和7年11月11日(火) | 9月~10月分 |
| 令和8年1月9日(金) | 11月~12月分 |
| 令和8年3月11日(水) | 1月~2月分 |
受給資格の喪失
- 受給資格者の父または母が婚姻した場合
- 受給資格者の父または母が異性と同居した、またはそれに準ずる状況の場合(事実婚)
- 児童が児童福祉施設等に入所した、または里親委託された場合
- その他、児童を養育しなくなった場合 など
公的年金等を受給している場合
また、児童が公的年金等を受給している、または、児童が配偶者受給の障害年金の加算対象になっている場合は、その受給額または加算額のひと月当たりの金額を手当額から差し引きます。
公的年金等受給開始の届出手続きが遅れたり、公的年金等を過去に遡って支給された場合は、既に支給済みの手当の一部または全部を返還していただくことがあります。
公的年金等の申請を行った場合は、お早めにご連絡ください。
障害基礎年金注3を受給している方(令和3年3月分手当から適用)
これまで、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が手当額を上回る場合、手当が支給されませんでしたが、令和3年3月分の手当から、手当の額が公的年金等の子の加算部分の額を上回る場合、その差額が手当として支給されます。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等のみを受給している方(障害基礎年金等を受給していない方) 注4は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が手当額を下回る場合は、その差額分が手当として支給されます。
また、令和3年3月分手当以降は 、 障害基礎年金等を受給している手当受給資格者 の 「 所得 」 に非課税公的年金給付等注5が含まれます 。
注3 国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
注4 障害基礎年金等を受給していない方で、 遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障
害年金以外の公的年金等や障害厚生年金 (3級)を受給している方。
注5 障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。
その他手続きが必要なとき
| 種類 | 時期 | 添付書類等 | 備考 |
| 現況届 | 毎年8月 | 毎年8月に通知いたしますので、こども支援課へ郵送または窓口にてご提出ください。 期日までに提出がない場合は、翌年1月以降の手当が支給できないことがあります。 なお、2年間提出がない場合は、時効により受給資格が喪失します。 |
|
| 額改定請求書 | 対象児童が 増えたとき |
対象児童の戸籍謄本 | 請求の翌月分から手当が増額されます。 |
| 額改定届 | 対象児童が 減ったとき |
事由発生の翌月分から手当が減額されます。 | |
| 喪失届 | 受給資格が なくなったとき |
事由発生の月分まで手当が支給されます。 | |
| 住所変更及び 支払金融機関 変更届 |
市内で転居したとき | ||
| 振込先口座を 変更するとき |
通帳等の写し | ||
| 市外転出届 | 市外に転出したとき | 転出先で手続きをしてください。 | |
| 氏名変更及び 支給要件変更届 |
氏名を変更したとき | 戸籍謄本 | |
| 支給要件が 変更になったとき |
|||
| 受給者死亡届 兼未支払手当 請求書 |
受給者が 死亡したとき |
手当対象児童の通帳等の 写し |
戸籍法の届出義務者が提出してください。 |
|
証書亡失届兼
再発行請求書 |
手当証書を 紛失したとき |
||
| 公的年金等 受給状況届 |
公的年金等を受給 開始したとき 公的年金等受給額が 変更されたとき |
公的年金等の受給額が わかる書類 |
|
| 辞退届 | 手当の全部が停止されていて、今後も所得制限限度額を下回る見込みがない等の理由により、受給資格を辞退したいとき | 受給者の運転免許証、医療保険の資格確認書等またはこれに相当するもの、マイナンバーカード等の写し | 辞退届提出後に児童扶養手当の認定が必要になった場合は、再度、認定請求書の提出が必要です。 |
手当を5年以上受給している場合
受給資格者(養育者を除く)が手当を受けてから5年以上経過する、または支給要件に該当してから7年以上経過する場合(ただし、認定および額改定請求時に、3歳未満の児童がいる場合を除く)は、手当の支給額が2分の1に減額されます。なお、以下の要件に該当する場合は、手続きをすることによって、減額されません。
手当額が減額されない要件
- 就業している
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている
- 身体上または精神上の障がいがある
- 疾病、負傷または要介護状態等により就業することが困難である
- 監護する児童または親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、介護する必要があるため就業することが困難である
手続き方法
手続きが必要な方には別途通知します。期限までにこども支援課へご提出ください。必要書類は「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」と「手当額が減額されない要件を確認できる書類等」です。