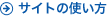1か月の利用者負担が上限額を超えたとき
同一世帯内で1か月にサービスにかかる利用者負担額が下表の上限額を超えたときは、超えた分が「高額介護(予防)サービス費」として払い戻されます。なお、利用料を支払ってから2年経過すると払い戻しを受ける権利がなくなりますので、ご注意ください。
ただし、このような費用は対象となりません
●福祉用具購入費の利用者負担分 ●支給限度額を超える利用者負担分
●住宅改修費の利用者負担分 ●部屋代・食費・日常生活費など
利用者負担の上限額(1か月)
| 利用者負担段階区分 | 上限額(世帯合計) | |
| ●生活保護、中国残留邦人等支援給付の受給者 | 15,000円(個人) | |
| ●世帯全員が市町村民税非課税の方 | 24,600円 | |
| ●世帯全員が市町村民税非課税で ・課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 ・老齢福祉年金の受給者 |
15,000円(個人) | |
| ●世帯のどなたかが市町村民税課税の方 | 44,400円 | |
| 現役並み所得 相当世帯の方 |
●課税所得145万円以上380万円未満 | 44,400円 |
| ●課税所得380万円以上690万円未満 | 93,000円 | |
| ●課税所得690万円以上 | 140,100円 | |
申請方法
払い戻しを受けるには、「介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」を介護福祉課に提出する必要がありますが、対象になる方には市から申請書を送付しています。(申請書はこちら)
介護保険と医療保険の利用者負担額が高額になったとき
同一世帯内(各医療保険制度上の世帯)で1年間(8月~翌7月)の介護サービス費と医療費の両方の自己負担額が下表の限度額を超えたときは、申請により超えた分が「高額医療合算介護(予防)サービス費」として払い戻されます。※「医療保険」・「介護保険」の自己負担額のいずれかが0円である場合は支給されません。
※各医療保険制度上の世帯が対象です。住民基本台帳上の世帯とは異なり、住民基本台帳上同世帯でも医療保険制度が別であれば合算できません。
高額医療・高額介護合算制度の負担限度額(年額/8月~翌7月)
|
所得区分
(基礎控除後の総所得金額等)
|
限度額 |
| 市町村民税非課税世帯 | 34万円 |
| 210万円以下 | 60万円 |
| 210万円超600万円以下 | 67万円 |
| 600万円超901万円以下 | 141万円 |
| 901万円超 | 212万円 |
| 所得区分 | 限度額 | |
| 市町村民税非課税世帯 | 低所得Ⅰ(所得が一定以下) | 19万円 |
| 低所得Ⅱ | 31万円 | |
| 一般(市町村民税課税世帯) | 56万円 | |
| 現役並み所得者 | 課税所得145万円以上 | 67万円 |
| 課税所得380万円以上 | 141万円 | |
| 課税所得690万円以上 | 212万円 | |
※ 毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されます。
申請方法
高額医療合算介護(予防)サービス費は、「医療保険」と「介護保険」の双方から、自己負担額の比率に応じて支給される仕組みになっています。支給を受けるためには、加入している医療保険者に申請が必要です。ただし、基準日と計算期間の関係で申請窓口が異なりますので、下記の「基準日と計算期間の窓口」をご覧ください。(参考)
食費・部屋代の利用者負担軽減について
低所得の方の施設利用が困難とならないように、所得に応じた負担限度額が設けられています。負担限度額を超えた分は、「特定入所者介護サービス費」として介護保険から給付されます。軽減の対象となる条件
下記の(1)(2)いずれかの要件を満たす方が対象になります。(1)生活保護を受給している方
(2)①~③のすべてに該当する方
① 世帯全員が市町村民税非課税
② 配偶者が市町村民税非課税 ※配偶者が別世帯の場合でも市町村民税課税であれば対象外です。
③ 預貯金等の額が以下の基準にあてはまる方
| 段階 | 配偶者なし | 配偶者あり (夫婦の合計額) |
| 第1段階 | 1,000万円以下 | 2,000万円以下 |
| 第2段階 | 650万円以下 | 1,650万円以下 |
| 第3段階① | 550万円以下 | 1,550万円以下 |
| 第3段階② | 500万円以下 | 1,500万円以下 |
軽減内容
| 利用者負担段階 | 食費 | 居住費 | |||||||
| 施設 サービス |
短期入所 サービス |
ユニット型個室
|
ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 | 多床室 | ||||
| 第1段階 | 生活保護受給者又は中国残留邦人等支援給付受給者 | 300円 | 300円 | 880円 | 550円 | 550円 (380円) |
0円 | ||
| 世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金の受給者 | |||||||||
| 第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万9千円以下の方 | 390円 | 600円 | 880円 | 550円 |
550円
(480円) |
430円 | ||
| 第3段階① | 世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万9千円超120万円以下の方 | 650円 | 1,000円 | 1,370円 | 1,370円 |
1,370円
(880円) |
430円 | ||
| 第3段階② | 世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が120万円超の方 | 1,360円 | 1,300円 | 1,370円 | 1,370円 |
1,370円
(880円) |
430円 | ||
※施設が定める食費及び部屋代が基準額を下回る場合は、施設の定める額と自己負担限度額の差額が給付されます。
申請方法
負担の軽減を受けるためには、介護福祉課へ申請し、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、サービス事業者に提示する必要があります。(申請書はこちら)
旧措置入所者の利用者負担の特例
平成12年3月31日までに特別養護老人ホームに入所した方で、引き続きその施設に入所される方は、現行の費用徴収額を基本的に上回らないよう、所得に応じて利用者負担・食費・部屋代を軽減します。課税層に対する特例軽減措置
原則、市町村民税課税世帯又は配偶者が市町村民税課税の場合は認定されませんが、施設入所などの費用を負担することで、在宅における世帯員の生計が困難になるような場合は、一定の要件を満たした方について対象となる場合があります。詳しくは介護福祉課へお問い合わせください。社会福祉法人による利用者負担軽減制度
社会福祉法人の指定事業所が提供するサービスを受ける際に、自己負担額が軽減される場合があります。軽減の対象となる条件
下記の(1)(2)いずれかの要件を満たす方が対象になります。(1)生活保護を受給している方
(2)以下のすべてに該当する方
● 世帯全員が市町村民税非課税
● 年間収入が単身世帯で150万円以下であること
(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること)
● 預貯金等の額が単身世帯で350万円以下であること
(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること)
● 居住している以外の不動産を所有していないこと
● 別世帯課税者の税又は医療保険の扶養になっていないこと
● 介護保険料を滞納していないこと
対象サービスと軽減内容
| 対象サービス | 対象者 | 軽減内容 |
| ① 訪問介護(予防訪問介護相当サービスを含む。) ② 通所介護(予防通所介護相当サービスを含む。) ③ 短期入所生活介護(予防を含む。) ④ 認知症対応型通所介護 ⑤ 小規模多機能型居宅介護(予防を含む。) ⑥ 地域密着型通所介護 ⑦ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ⑧ 介護老人福祉施設 ⑨ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ⑩ 複合型サービス ⑪ 夜間対応型訪問介護 |
上記要件のすべてに該当する方 |
サービスの利用者負担額、食費、居住費の25%を軽減
※利用者負担段階が第1段階の老齢福祉年金の受給者は50%
|
| 生活保護受給者 | 個室の居住費の全額を軽減 |
※「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けていない方は、③・⑦・⑧の食費及び居住費が軽減対象外となります。
(申請書はこちら)
民間等介護保険サービス利用者負担額軽減制度(苫小牧市独自の制度)
社会福祉法人以外の指定事業所が提供するサービスを受ける際に、自己負担額が軽減される場合があります。軽減の対象となる条件
下記の(1)(2)いずれかの要件を満たす方が対象になります。(1)生活保護を受給している方
(2)以下のすべてに該当する方
● 世帯全員が市町村民税非課税
● 年間収入が単身世帯で150万円以下であること
(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること)
● 預貯金等の額が単身世帯で350万円以下であること
(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること)
● 居住している以外の不動産を所有していないこと
● 別世帯課税者の税又は医療保険の扶養になっていないこと
● 介護保険料を滞納していないこと
対象サービスと軽減内容
| 対象サービス | 対象者 | 軽減内容 |
| ① 訪問介護(予防訪問介護相当サービスを含む。) ② 通所介護(予防通所介護相当サービスを含む。) ③ 短期入所生活介護(予防を含む。) ④ 地域密着型通所介護 |
上記要件のすべてに該当する方 |
サービスの利用者負担額、食費、部屋代の25%を軽減
※利用者負担段階が第1段階の老齢福祉年金の受給者は50%
|
| 生活保護受給者 | 個室の滞在費の全額を軽減 |
(申請書はこちら)