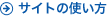開催場所 苫小牧市役所8階 81会議室
出席者 東会長、福井副会長、高野委員、江川委員、 阿部委員、岡委員、長岡委員、事務局職員
会議次第
1 開会2 会議
(1) 議論の整理・集約に向けて更に検討が必要である個別論点について
(2) その他
3 閉会
会議資料
 次第(42.94 KB)
次第(42.94 KB) 議論の整理・集約に向けて更に検討が必要である個別論点(73.73 KB)
議論の整理・集約に向けて更に検討が必要である個別論点(73.73 KB) 第4 住民投票の対象事項(130.42 KB)
第4 住民投票の対象事項(130.42 KB) 第5 住民投票の投票資格及び請求資格(83.39 KB)
第5 住民投票の投票資格及び請求資格(83.39 KB) 第7 外国人住民の投票資格及び請求資格(125.38 KB)
第7 外国人住民の投票資格及び請求資格(125.38 KB) 第8 住民投票の請求権者(発議権者)及び署名要件(106.94 KB)
第8 住民投票の請求権者(発議権者)及び署名要件(106.94 KB) 第10 成立要件 第15 再請求の制限期間(113.80 KB)
第10 成立要件 第15 再請求の制限期間(113.80 KB) 既に議論が終了している個別論点(主な検討結果)(117.53 KB)
既に議論が終了している個別論点(主な検討結果)(117.53 KB)
会議録
 苫小牧市住民投票条例市民検討懇話会(第5回)会議録(326.99 KB)
苫小牧市住民投票条例市民検討懇話会(第5回)会議録(326.99 KB)
開催概要
(1) 議論の整理・集約に向けて更に検討が必要である個別論点について
第4 住民投票の対象事項
「市政の重要な課題」については、本市が想定している住民投票の対象事項の本質を外形的に明示することにより、本市における住民投票の対象事項の位置付けを明確にすることを目的として規定することを確認しました。「住民投票の対象事項から除く必要があると考えられる事項」については、「市の権限に属さない事項(市の意思を表明する場合を除く。)」、「法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項」、「市の組織、人事又は財務に関する事項」、「専ら特定の市民又は地域に関する事項」、「その他住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項」とすることを確認しました。
第5 住民投票の投票資格及び請求資格
住民投票の投票資格及び請求資格については、現行の選挙権年齢や実務上の観点から20歳とすることについても検討すべきとの意見が出されました。しかし、市民参加条例における市民政策提案ができる年齢が社会人としての年齢を考慮して18歳以上であることを踏まえ、整合性を図る必要があるとの考え方が示されました。また、選挙権年齢や成人年齢の引下げが、今後、国政において議論されることが考えられる中で、若年層の政治的関心を喚起する意味からも18歳以上を基本とすることが望ましいことを確認しました。住所要件については、住民投票の投票資格についても選挙と同様に「少なくとも一定期間をそこに住み、地縁的関係も深く、かつ、ある程度団体内の事情に通じていることが必要である。」と考えられることを理由として、引き続き3か月以上本市の区域内に住所を有する者を投票資格者とすることを確認しました。
第7 外国人住民の投票資格及び請求資格
日本人住民と同様に、外国人住民についても市との関わりにおいてまちづくりに関係する存在であることから、まちづくりに参加することができるため、本市の区域内に住所を有する外国人住民についても、住民投票の権利の対象者とすることを確認しました。住民投票の権利の対象者となる外国人住民の範囲についての明確な区分の基準はないため、本市における外国人住民の数等を勘案して判断することとなりますが、現時点においては、今後も継続して在住する蓋然性が高いと考えられる「特別永住者」及び「永住者の在留資格をもって在留する者」に限り、対象とするのが望ましいことを確認しました。
投票資格者名簿の被登録要件における外国人住民の年齢要件及び住所要件については、日本人住民の場合と同様とすることを確認しました。また、外国人住民の投票資格者と請求権者については、日本人住民の場合と同様に「住民投票の投票資格を有する者は、住民投票の請求資格を有する」こととすることを確認しました。
外国人住民の投票資格者名簿への登録方法については、日本人住民の場合と同様に、地方公共団体の住民に関する事務として住民基本台帳から対象者を抽出し、投票資格者名簿に登録することを確認しました。
第8 住民投票の請求権者(発議権者)及び署名要件
議会からの請求、市長自らの発議について、これらを設定する場合に留意すべき点について確認しました。住民の意思として表明される住民投票の結果は十分に尊重されることが求められるため、市長選挙における当選者の得票数程度の署名数が必要であるとの結論に至りました。また、地方自治法の直接請求(議会の解散請求、議員の解職請求、長の解職請求)に必要な署名数が3分の1であること、常設型住民投票条例が諮問型であることを踏まえ、4分の1程度とするのが適当であることを確認しました。
第10 成立要件
成立要件の設定の有無にかかわらず、必ず開票され、結果が公表される必要があるという共通認識について確認しました。その上で、成立要件を設け、これを満たしたときに住民投票の結果について尊重義務を発生させる制度とすべきとの意見が出されました。この場合における成立要件については政治的メッセージとしての指標にもなること、また、成立要件を満たさない場合の投票結果については条例上の尊重義務が発生しないことを確認をしました。具体的な成立要件としては、投票資格者総数の2分の1以上が投票し、かつ、投票者の過半数の意思を全体の意思とみなすことに合理性があるとの意見が出されました。
一方、必ず開票され、結果が公表されるのであれば、成立要件を満たさない場合であっても事実上の尊重の要請が発生することが考えられ、また、成立要件の具体的な数値に明確な根拠を持てないとすれば、諮問型の条例設計であることを踏まえて成立要件を設ける必要はないとの意見も出されました。
そのため、成立要件の設定については、両論を併記とすることとしました。
第15 再請求の制限期間
投票の結果については、開票結果が示されるかどうかにかかわらず、不成立の場合であってもそれは住民の意思であること、また、一度示された意思を尊重するため、一定の期間、事実上の効力を持たせることが必要であることを確認しました。また、住民投票は、多くの時間、費用、労力等を費やした上で行われるため、制度が濫用されることを避ける必要があることについても確認しました。そのため、成立要件を設けて投票結果が不成立であった場合における同一事案の再請求についても、これを制限することを確認しました。
(2) その他
次回は、3月14日(木)に開催する方向で調整することとしました。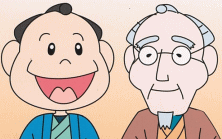
※ 開催概要は速報であり、後で修正する場合があります(文責:市民自治推進課)。