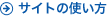開催場所 苫小牧市役所9階会議室
出席者 東会長、福井副会長、高野委員、江川委員、岡委員、佐々木委員、長岡委員、事務局職員
会議次第
1 開会2 委嘱状交付式
3 総合政策部長挨拶
4 委員紹介・事務局紹介
5 会長・副会長の選出
6 会議
(1) 会議及び会議録の取扱いについて
(2) 懇話会の検討スケジュール予定について
(3) 住民投票制度に係る個別論点の検討について
(4) その他
7 閉会
会議資料
 次第(59.27 KB)
次第(59.27 KB) 苫小牧市住民投票条例市民検討懇話会委員名簿(54.78 KB)
苫小牧市住民投票条例市民検討懇話会委員名簿(54.78 KB) 苫小牧市住民投票条例市民検討懇話会設置要綱(65.61 KB)
苫小牧市住民投票条例市民検討懇話会設置要綱(65.61 KB) 苫小牧市住民投票条例市民検討懇話会会議録の取扱いについて(73.20 KB)
苫小牧市住民投票条例市民検討懇話会会議録の取扱いについて(73.20 KB) 苫小牧市住民投票条例市民検討懇話会スケジュールについて(案)(115.05 KB)
苫小牧市住民投票条例市民検討懇話会スケジュールについて(案)(115.05 KB) 住民投票制度についての検討結果(提案)(住民投票制度を考える会 平成23年3月29日提出)(73.10 KB)
住民投票制度についての検討結果(提案)(住民投票制度を考える会 平成23年3月29日提出)(73.10 KB)
 第1 住民投票制度の意義と位置付け(1.55 MB)
第1 住民投票制度の意義と位置付け(1.55 MB) 第2 個別設置型条例と常設型条例(1.55 MB)
第2 個別設置型条例と常設型条例(1.55 MB) 第3 投票結果に対する拘束力と尊重義務(474.55 KB)
第3 投票結果に対する拘束力と尊重義務(474.55 KB) 第4 住民投票の対象事項(171.92 KB)
第4 住民投票の対象事項(171.92 KB) 第5 住民投票の投票資格及び請求資格(294.15 KB)
第5 住民投票の投票資格及び請求資格(294.15 KB)
会議録
 苫小牧市住民投票条例市民検討懇話会(第1回)会議録(309.84 KB)
苫小牧市住民投票条例市民検討懇話会(第1回)会議録(309.84 KB)
開催概要


各委員に委嘱状が交付され、総合政策部長が挨拶を行い、委員及び事務局の紹介が行われました。
会長に東委員、副会長に福井委員が選出されました。
(1) 会議及び会議録の取扱いについて
会議及び会議録の取扱いについては、発言者氏名について、個人名を表記する取扱いとすることとし、了承されました。(2) 懇話会の検討スケジュール予定について
スケジュール案について、おおむね了承されました。(3) 住民投票制度に係る個別論点の検討について
第1 住民投票制度の意義と位置付けについて
住民投票制度が必要である理由、その意義について確認がされました。
住民投票の実施については、当該案件について十分に事前の議論を重ねることが大切であり、他の参加の仕組みで解決がなされなかった場合や、議論を重ねた末に合意に至らなかった場合等で実施されることが確認されました。
住民投票制度については、議会や長の固有の権限を侵すものではなく、間接民主制を補完する制度であることが確認されました。
第2 個別設置型条例と常設型条例
住民投票条例については、「個別設置型条例」と「常設型条例」の2つに大別されること、また、それぞれの特徴について確認をしました。
常設型条例を制定することは、苫小牧市自治基本条例第6条における仕組みとしての住民投票制度が担保されることになることを確認しました。
第3 投票結果に対する拘束力と尊重義務
住民投票による投票結果について法的拘束力を持つ「拘束型」の住民投票条例を制定することは困難であること、また、この前提として考えられる「諮問型」の住民投票条例における尊重義務についても確認しました。
第4 住民投票の対象事項
市政の重要な課題について行うことができるとされている住民投票について、その対象となる具体的対象についての議論を進めました。
市政の重要な課題についてどのように捉えるべきかの議論が行われました。また、市政の重要な課題についてどのように市が判断を行うのかといった裁量の問題についても、議論が行われました。
市政の重要な課題から対象事項として除外するいわゆるネガティブリストについては、多岐に渡ることから、再度、検討を行うこととしました。
第5 住民投票の投票資格及び請求資格
住民投票の投票資格及び住民投票の実施を請求するための資格についての年齢要件及び住所要件についての検討を行いました。年齢要件については、公職選挙法の選挙権年齢である20歳以上とするのか、20歳未満の特定年齢以上とするのかについて議論を行い、今後も、引き続き検討することとしました。
住所要件についても、引き続き検討することとしました。
(4) その他
次回は、11月14日(水)に開催する方向で調整することとしました。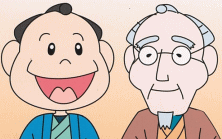
※ 開催概要は速報であり、後で修正する場合があります(文責:市民自治推進課)。