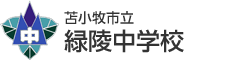緑稜の教育
学校教育は、子どもの人格形成の育成に寄与することを目的に行われます。そのために、急激な社会の変化や時代の求めを読みとりながら、未来を担う子ども達が実社会に巣立つとき、今まで育んできた「生きる力」を存分に発揮して充実した人生を切り開いていけるよう、人としての基礎・基本を身に付けることがなによりも大切です。更に、本当の学力を身につけさせるためには、まず心づくりが基盤となることを踏まえて進めることが重要と考えています。
こうした考えに立って、全教職員が同じ歩調で、一丸となって生徒一人一人との人間的なふれあいを通して、生徒のよさを見つけ、可能性を最大限に伸ばすよう努力すると共に、家庭の協力はもちろん、地域とも連携しながら、着実な生徒の成長を願い教育を進めます。
学校経営の重点
令和7年度グランドデザイン
 令和7年度グランドデザイン(416.99 KB)
令和7年度グランドデザイン(416.99 KB)
令和7年度の経営の重点と具体的方策
教育課程 「資質・能力」の育成を見据えた教育課程の充実
・教科等横断的な視点での教育課程の編成
・教育活動全体を通しての情報活用能力、課題解決能力、表現力の育成
・3年間を見通した進路指導とキャリア教育の充実(キャリアパスポートの活用等)
・教育課程に位置付けた地域の人的・物的資源の活用
・小中連携による9年間を身とした教育活動の充実(Tomakomai All-9)
組織運営 協働するチームづくりと働きやすい環境づくり
・年齢や役職に捉われず、職員の心理的安全性が確保された職場(チーム)づくり
・対話を大切にし、共通の目的に向かって連携、協働する組織運営
・課題(失敗含)の原因や改善策の共有と学びに変えられる信頼関係の醸成
・運営委員会や特別委員会等(学校教育力向上エリア会議含)の機能化
学年・学級経営 生徒にとって安心・安全な居場所や絆となる学級や学年づくり
・秩序ある学年経営を基盤とした格差のない学級づくり
・基本的な生活習慣の定着(わきまえる、時間を守る、あいさつや礼儀等)
・多様性を尊重し互いの良さを認め合える温かい人間関係づくり
・個々の生徒に寄り添う姿勢と居場所や絆づくり(いじめ根絶、不登校対応等)
・生徒の主体的な活動の育成(学年スタッフの意図的・計画的な働きかけ)
研修活動 日常の実践に結びつく校内研修の充実体的な学力向上のためのプラン
・主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の推進
◇生徒の主体的な活動の育成(学年スタッフの意図的・計画的な働きかけ)
◇生徒を主語とした共通取組場面の適切な位置付け
◇ICTの効果的な活用の探求と課題や改善についての共有
◇共通取組事項を基盤とした指導と評価の一体化
・研修の成果を校内研修に環流させる体制づくり(資料提供、研修だより等)
教育環境の整備 誰もが居心地の良い、利用しやすい環境づくり(UD化)
・言語環境の整備(教職員が範となる言動、生徒の発表機会の意図的な設定等)
・校内環境の整備(清掃活動、掲示物の工夫、図書室の利用促進、空き教室活用)
・ICT環境の整備(生徒用タブレット、モニター、授業用PC、デジタル教材等)
・定期の安全点検による危険箇所・破損箇所の把握と補修
家庭・地域との連携 家庭・地域との信頼やつながりを育む学校づくり
(1
・地域の教育資源を積極的に活用したキャリア教育とふるさと教育の充実
・学校教育力向上エリア会議及びコミュニティ・スクール(CS)の効果的な活用
・学校ホームページ、さくら連絡網、学校だより等による積極的な情報の発信
・家庭との連携による望ましい生活習慣や学習習慣の定着
危機管理 未然防止・初期対応を軸とした危機管理体制の確立
・「自助」、「共助」を軸とした防災教育の推進(胆振防災教育デーの取組等)
・生徒の安心・安全の確保を最優先に考えた初期対応と管理体制の強化
・非常災害時や事故発生時の迅速な対応や感染症予防対策の徹底
・いじめ防止基本方針に基づいた組織的な対策と対応の推進
職場環境の整備 ワークライフバランスを意識した働き方改革の推進
・働き方改革推進のコアチーム(運営委員会)の活性化
・業務内容の効率化の推進(自分事として、学年・分掌としての効率化)
・定時退勤日の着実な実施と年次有給休暇等の休暇取得の促進
・部活動の地域展開に向けた校内体制の整備